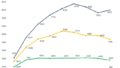日弁連でひまわり基金20周年を記念してシンポジウムが開催されたということで、弁護士ドットコムが記事を出していたのが目に入ってきた。
この記事に対する反応は色々とあって、結構びっくりしている。
ただ、昔とずいぶん違うと感じるのは、若い人ばかり地方に行かせるようなことをするな、というような論調が見られることであった。これは、少々意外であった。
思い出話のようなもの
そういうことで、もう自分も年寄りに足を突っ込んでいる世代だと思いつつ、若干の思い出話のようなものをしてみる。
うちの事務所のパートナーは根室の公設事務所に勤めたことがあった。それで聞いてみると、かつて根室には武富士しかサラ金がないという時代があったので、お金に困った人は武富士でお金を借り、それが軒並み過払いになる状況が生じていたというのである。似たようなことは、それこそ全国津々浦々で起こっていたであろう。
もちろん、公設事務所の草創期の先生方は大変な苦労をしているし、離島などでの困難は大きい。ただ、場所や時期にもよるが、かつての公設事務所は割と稼げたところもあったのである。元々、弁護士がいない場所で仕事をする社会的な意義は極めて大きいから、若い人も多少の不便はあっても地方へ行って頑張ってみよう、という雰囲気はあったのだ。
そのようなことは公設事務所に限ったことでもなく、当職が就職したころの当地の弁護士は少なかったから、給料の3倍を個人事件で稼ぐ時期もあり大いに「やりがい」を感じた。もっとも、事件を受け過ぎても良いことではない。
過払いバブルが去り…
今はどうか。地方の経済は人口減少と共に縮小し、良くても横ばいというところである。過払いバブルも去った。どこの地方でも弁護士数は平均2~3倍になっているから、単純な割り算ができれば、そこで何が起こるか想像するのは難しいことではない。
弁護士はどの程度稼いだら足りるのか?という問題は、どこで、誰と、どのような生き方をするのかということによっても異なるから、一概にはいえない。とはいえ、企業や役所で勤めても所得の期待値が大して変わらないかそれより劣るというレベルでは、参入コストが高く、稼働開始年齢も遅れ、フリンジ・ベネフィットにも乏しいこともあって、弁護士は職業的魅力のかなりの部分で負ける。そうすると、新規参入者が業種を選択する時点で弁護士は選ばれないし、業態を選択する時点でも地方の街弁は選ばれなくなる。
近年、新規登録者がいない弁護士会が相当数出ているのはそういうことなのである。司法試験の合格者がいくら増えたところで、放っておいて地方の弁護士は増えることにはならない。
当職の現状にしても、同じ大学卒の同年代で企業や役所に入った連中と比べたらこりゃあ負けてるなあ!と思ったりすることも、ないわけではない。単位会の要職みたいなものを務めるに至っても実態はその程度の場合もあったりするのである。
但し、他の人の名誉のために言っておくと、地方で商機をきっちり捉えて名士化しているような人はもちろんそうではない。そういう人こそ公益活動をどんどん担うべきである。
バランスシート上の「やりがい」
さて、そういった生存環境の中で仕事に何を求めるのか、ということは我々在野法曹に課せられた永遠のテーマである。
ずいぶん前の話ですが、ある若い先生から「生涯バランスシート」なるものを見せられましてね。何かというと、大企業のサラリーマンと弁護士の平均的な生涯年収を比較したもの。弁護士のほうが低く、投下資本や労働量からすると「ワリに合わない」と言うわけです。しかし、そのバランスシートには「のれん代」じゃないけど「やりがい」という項目がなかった。自治の下で、まさに人権擁護、社会正義の実現を目指して好きな分野で活動できるという、目に見えない付加価値があるんじゃないかと。数字を凌駕する魅力ある仕事だということをどう伝えていくか、法曹志望者が減る状況において極めて重要な課題です。
菊地先生は北海道のご出身である。一時、最高裁長官、検事総長、日弁連会長の法曹三者のトップがみな北海道出身者で占められた時期があった。そのことを好意的に報じていた向きもあったが、自分のところの島から優れた人材が続々と流出していったことが本当に喜ばしいことなのだろうか、とは思った。
菊地先生も、若い人が抱えている現状への不満や将来への不安といった自然な心情を無視して「やりがい」を強調するのであれば、ぜひ、東京のど真ん中で良く分からない都市再開発とか手掛けてないで自ら範を示すべく故郷に戻ってお仕事をされてはどうだろうか。自ら北海道新聞に「人口減や高齢化が進んでも法的需要が減るわけではない」と力強いコメントをされていたこともあるくらいなので、北海道民の一人としては大いに期待している。
「仕事」があるのかないのか
一方、飛ぶ鳥を落とす勢いで伸長している事務所の大ボスさんが、なかなか興味深いことをおっしゃっていたのを目にした。
もし今、自分がゼロから事務所を作り直すとしたら、まずは地方都市に行く。弁護士が少なく競争がない地方都市なら、億単位の売上を目指せる。地方都市を中心に多店舗展開し、資金力をつけてから、満を持して大都市に進出する。 https://t.co/Vkstzx5ejC
— 酒井将 (@sakaisusumu_vb) December 19, 2020
酒井先生のご意見は、法曹人口を増加させればそのような発想も出てくるということで、司法制度改革の一つの帰結といえる。ただ、地方でガチで金稼ぎにフォーカスして勝ち逃げる人が発生すると、問題が起こることは容易に想像できる。
すなわち、地方では「金にはならんけど法秩序を維持する上で期待されてる重要なお仕事」というものも相当量存在するため、その点を弁えていないとここから見えるのは太平洋でもオホーツク海でもなくスーパーレッドオーシャンになるという問題である。
これだから悩ましいのである。
つまり、「地方には弁護士の仕事はあるのかないのか?」と聞かれれば「ある」。しかし、そこで期待されている「仕事」は、地域の法秩序を維持するために不可欠でありながら、事業としては成り立たないものも少なくない。それがこの十数年の我々の経験から言えることである。
もうちょっと踏み込んでいえば、もともとパイの限られた地域で弁護士間の競争が激化すると、収益性の低い業務は顧みられなくなってしまうのである。手間が掛かる、実入りも少ない、その上重要顧客の維持獲得につながらない(競争が激化するとこの要素は特に重要である)、という性質の業務は、他に仕事がないからやる、ということにはならないのである。結果的に、法秩序を維持することが難しくなる場面も現れる。
法の支配を津々浦々にというスローガンは、ここに挫折を見るのである。
現実的には、弁護士の数が増えているにもかかわらず、一定の業務(法律扶助、成年後見、弁護士保険、当番弁護士、国選弁護人、無償かそれに近い官公署の委託業務など)の引き受け手の確保がだんだん厳しくなっているという形で、このような問題は既に起こっている。
そういうことだから、将来にわたって相応の待遇が見込まれなければあえて地方で弁護士として働きたいという人はなかなか来ないし、実際はそのような待遇を見通せないのに「やりがい」があるからどんどん来てくださいとは言えない。有利誤認表示みたいな人集めをしないことは、法曹としてのせめてもの良心であろう。
とはいえ、新入会員が全く入ってこなければ、地方の小規模な弁護士会は徐々に衰退の一途をたどるのみである。それはそれで頭が痛い。
弁護士の分布の意味
話は変わるが、大正から昭和に差し掛かる時期にかけて道東で一番弁護士が多かった街は網走であり、7人の弁護士がいた。それはかつて網走が捕鯨基地としての隆盛を極めていた時代のことである。ところが、網走は近年公設事務所ができるまでは弁護士不在となっていたくらいであるから、隔世の感がある。
また、貿易や金融の拠点として繁栄し北のウォール街との呼び声もあった戦前期の小樽には、17人の弁護士がいた。これは今よりも多い上に、当時で比較しても札幌の弁護士数の半分にも匹敵する数字である。
このように、弁護士の分布というものは昔から流動的であり、とりわけ、それは地域の経済の勢いに依存している。
昨今、東京に弁護士の新規登録者が集中しているのも、東京が人も物もカネも一極に巻きこみながら経済を発展させていっているからに他ならない。そのような社会の潮流に抗うのは全く一大事業であって、もはや弁護士業界が単独でなしうることではない。若い人たちが、都会で働きたい、組織に属したいというなら、それは今の日本社会では合理的な生き方でもあるから、そうでないのがあるべき姿だとは言えない。
まとめ
以上、地方に弁護士が足りないかどうかという件に関していえば、「足りない。お金にはならないけれども地域を支えるために不可欠な仕事をしてくれる弁護士が足りない。」ということになる。
しかし、果たして、どこにそんな都合の良い人材が存在するのであろうか。もちろん、たまたま熱意あふれる人が現れるなら、それは歓迎したい。問題は、個人の善意に頼らざるを得ない構造そのものにある。もしかしたら、司法の人的基盤を確立するという目的で設立されたロースクールは、霞を食って生きる仙人や、自己犠牲を厭わない聖人を量産して地方に送り出すことができる究極の可能性を秘めているのかもしれない。それができるというなら、人材難の解消は容易である。
もはや、そんなとぼけたことを言っている場合でもないが、なおしばらくは、人材難という問題と、各種の公益活動の停滞という問題は、地方の弁護士会の頭痛の種として残りそうな感じがしている。